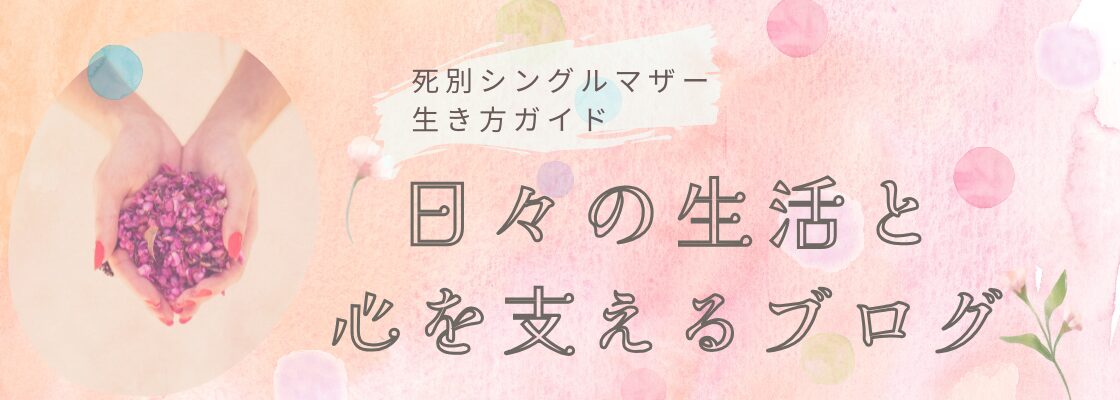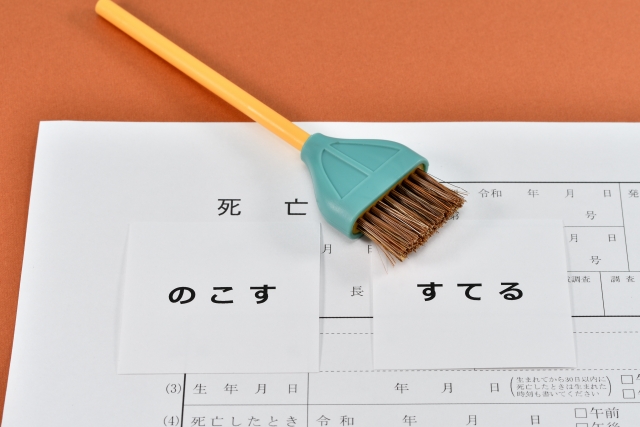
大切な人がいなくなった家の中の、大切な人の大切なもの。
亡くなった瞬間から、どうしていいかわからなくなりませんか?
また、その人しか知りえない、例えばその人宛の手紙とか、その人のメモの類いなど、モノから伝わる感情によって、さらに落ち込んでしまうこともあるでしょう。
今回は、大切な人の残した持ち物について、どうしていくか一緒に考えていきましょう。
これは一つの「正解」ではありません。
参考にしてもらって、自分なりの遺品整理を見つけてもらえたらと思います。
1. 遺品整理、いつするのが正解?
思い込みを捨てましょう

まず基本的に「すぐに整理しなければならない」という思い込みを手放すことが必要です。
喪失後のショックは人それぞれですが、ストレス値で言えば人生で最も高いからです。
大きなショックを受けた状態での判断力は、いつものそれとはまったく違います。
悲しいから、見ていると辛いからと感情のまま手放してしまい、後になって取り戻したいと思っても、それはなかなか難しい。
私の知り合いの方は、旦那様の愛車(自転車)を子供のお友達に譲り、そのあと取り戻したくなって平謝りして返してもらったというエピソードを聞きました。
これは取り戻せた成功パターンですが、家を手放して後悔したというお話も聞いたことがあります。こういった場合は取り戻すことが非常に難しい。
ですので、焦ることは禁物です。
その人のモノを見るだけでも辛いですよね。
例えば別室があるようでしたら、そこに押し込んでおくなど、しばらく目にしない場所に移動して、そのままにしておくのもいいかもしれません。
大切な人のモノのことを考えるより、自分の心を思うことが大切です。
順番はまず自分

心が落ち着いてからでもいくらでも考えられるので、モノをどうしよう?と思ったときには、「自分の心はどのように感じてるかな?」と問いかけてみてください。
「わからない」という思いが出たなら、それは時期尚早と理解し、一旦脇に置きましょう。
まずつらい事務手続きや、家計管理、子供のことなど、大切な人がいない生活スタイルがある程度見据えられる状態に整えるのが先です。
今の生活が見えてくるころに、きっと少し疲れが出るはずです。
身体の疲労も判断力を鈍らせます。
その疲れを癒してから、ゆっくりと考えていくといいでしょう。
2. 手放すのがつらい…迷ったときの考え方

モノを手放すのがつらいと感じた時、「手放さない」という選択肢もあることを覚えておいてください。
私の知り合いの方は、全てのモノを「変えたくない」と思い、ジップロックにきれいに梱包し、その人の生きていた状態を保つことを決めました。
それで心が安定するのであれば、それはその人の正解です。
遺品は手放すもの、という固定概念を開放しましょう。
手放す場合、「大切なもの」と「残すべきではないもの」は見極めていく必要があります。
感覚的な問題ですが、それは手に取ればなんとなくわかると思います。
気持ちが極端に落ちるものは、私は手放していいと思っています。
また先にも挙げましたが、その人へ宛てた手紙などの個人間のモノは、手放してもいいのではないかと思います。
その際、連絡先などを控えておくか、もし何か伝えたい気持ちが湧き起こったら、お手紙などでお礼を伝えてもいいかもしれませんね。
極端な私の例

私は夫のモノはほぼ手放しました。
見ると気分が落ち、一向に温かい気持ちにはならなかったからです。
「未来の自分の人生に必要なものは?」という問いかけをしたら、全て私の未来には必要ありませんでした。
冷たい言い方かもしれませんが、私は私であり、彼は彼だったということです。
また、利用できそうなものは彼の友達に形見分けをしました。
それは少し気持ちは楽になりました。
3. 故人の持ち物を手元に残す方法

どうしても手放せないと思う場合は「メモリアルボックス」を作るという方法もあります。
小さな箱を用意し、その中に納まるものだけを厳選するという方法です。
迷った場合は手放すというルールを作るとか、写真に残してデータ化するなど、自分なりの残し方を見つければ、多くのモノを手放すことができます。
また、お子さんがある程度大きい年齢でしたら、家族で話し合い、何を残すか判断するのも一つの方法です。
自分で決められない場合、周りの人に協力してもらい、意見を収集してみてください。
ただし、最終判断は必ず自分ですること。
これからは、自分が決める人生へシフトすることです。
自分の人生は自分のもの。
だれの責任でもありません。その訓練だと思って、判断は自分でしていきましょう。
4. 「手放したら忘れてしまうのでは…」という不安
物がなくても、思い出は消えない。

夫を亡くして14年目の私がお伝えしたいことは、大切な人の思い出は消えないということです。
私は夫の声も今でもすぐに思い出せます。
先ほども申し上げましたが、夫のモノはほぼゼロです。
それでも、忘れることはありません。
だから、「思い出はなくなってしまうかも…」という不安だけで、例えば一部屋埋めてしまったままでいるとか、倉庫を借りるなどは、本末転倒だと考えています。
私の場合は、モノに頼ることなく、心には必ず夫との思い出スペースが確保されていますし、それは元気な限りあり続けると確信しています。
6. 手放すすすめ

いろいろと語ってきましたが、私は基本的に、亡くなってしまった人のモノは手放した方がいいという考えです。
モノはそれほど多くなくても生きられます。それが彼を亡くして私が得た価値観です。
世の中に物はあふれています。
人は不足を感じた時に、物を購入しやすい。
夫を亡くして、多くの残されたモノを見た時に、私は虚しさしかありませんでした。
夫との生活に満たされていたはずなのに、あれこれ欲しがっていた自分がとても馬鹿だと思ったからです。
モノではなく、もっと大切にすべきものがたくさんありました。
ですから、私は今、本当にモノの少ない生活を送っています。
それがとても快適です。
私は個人的にモノを手放すことをおすすめしますが、もしモノがないと引き裂かれそうな気持ちになるのであれば、手元に置いておけばいい。
どちらでも、心の状態が健康になればそれが正解です。
目指すのは、「どう生きるのが快適か?」ということです。
どうしても頭の片隅から離れないなら、それは「深い」何かがあるということ。
でも、なくなれば考えなくなるものなら、手放してもいいかもしれません。
逆に、思い出すたびに温かくなるのであれば、そのモノは自分にとって必要なもの。
常に自分の心に問いかけて、自分の快適さを探してください。
そこにジャッジは必要ありません。
📣 大切な人を亡くしたあなたへ
「泣いても笑っても、どちらもあなたの人生」
死別後の不安や孤独を抱えながらも、もう一度“私らしく”生きていくためのヒントをお届けしています。
💌 個別でお話したい方はこちら
▶︎【公式LINE】https://lin.ee/l2rDBzV
🌸 カウンセリング・サポート内容の詳細はこちら
▶︎【公式HP】https://atelieaoihosi.crayonsite.com/
あなたのタイミングで、いつでものぞいてみてくださいね🌷